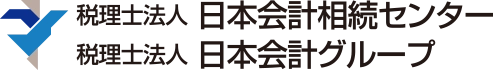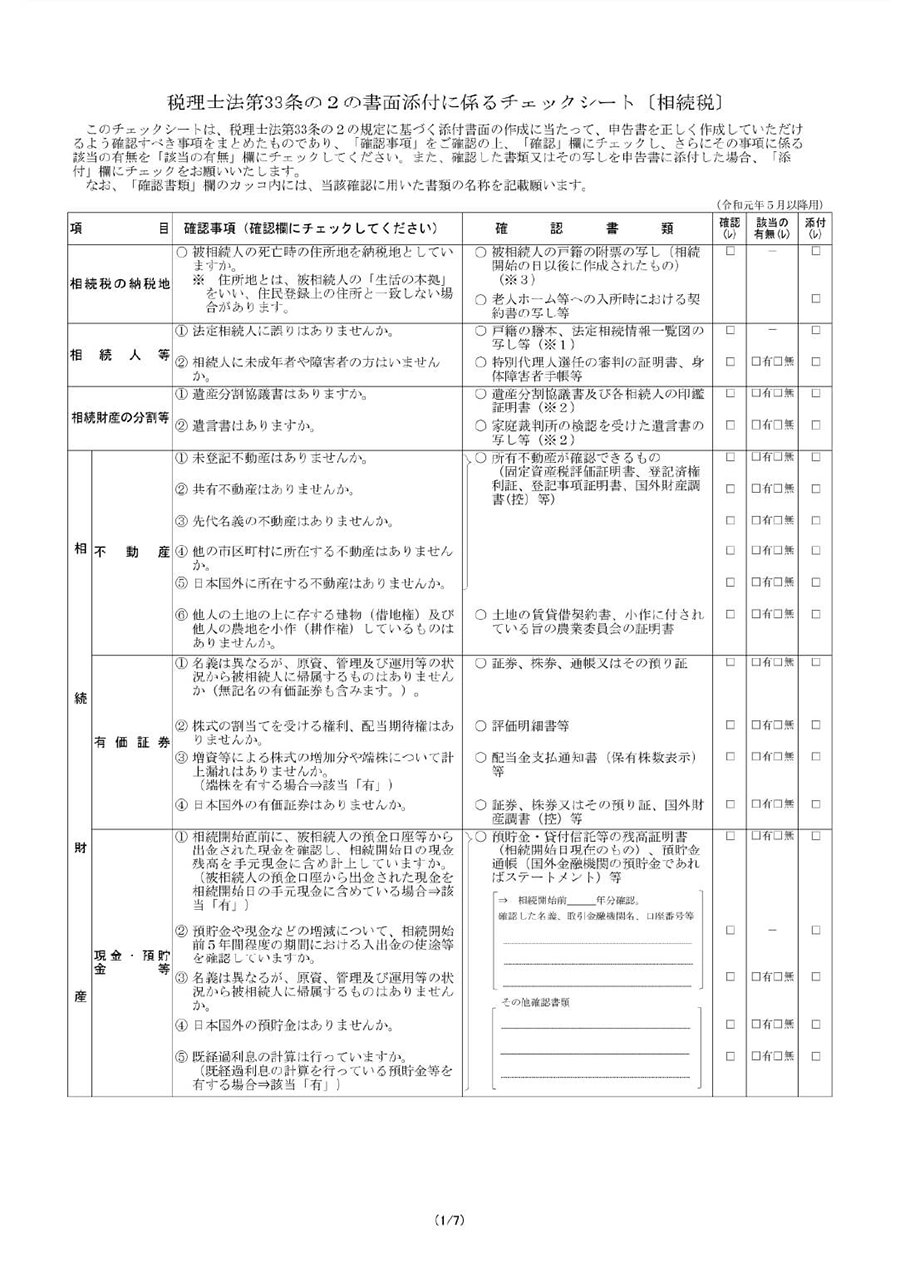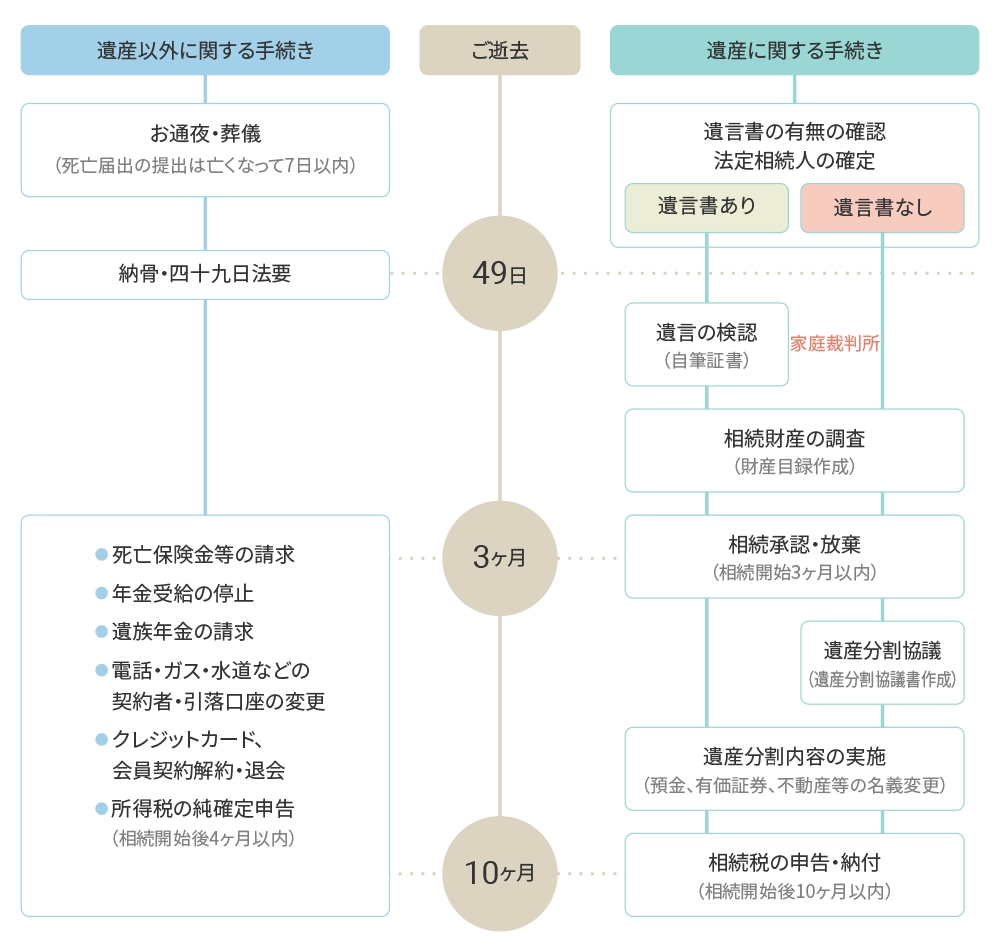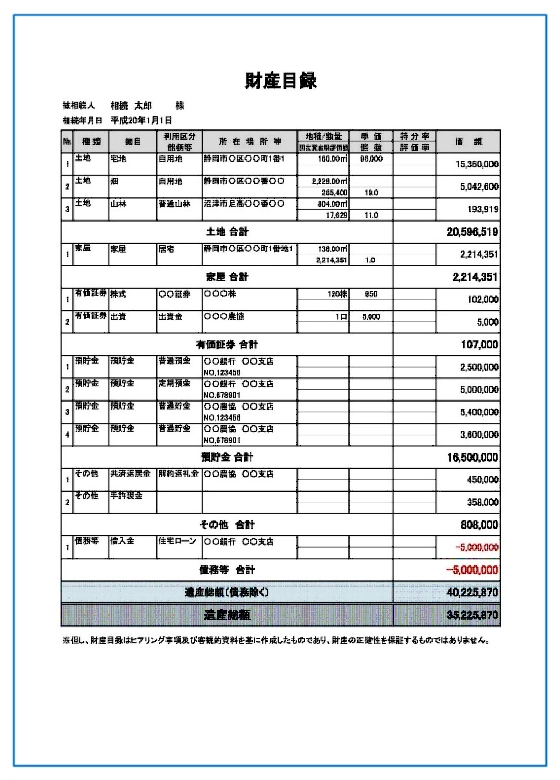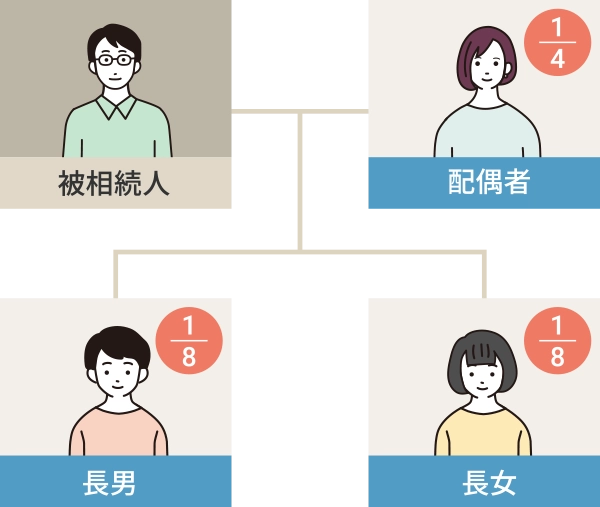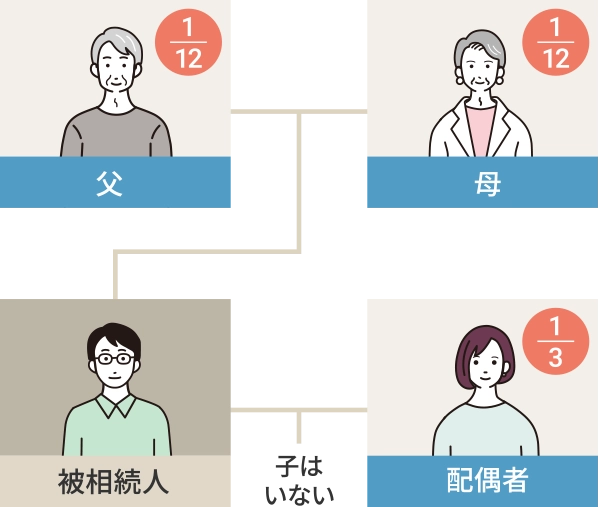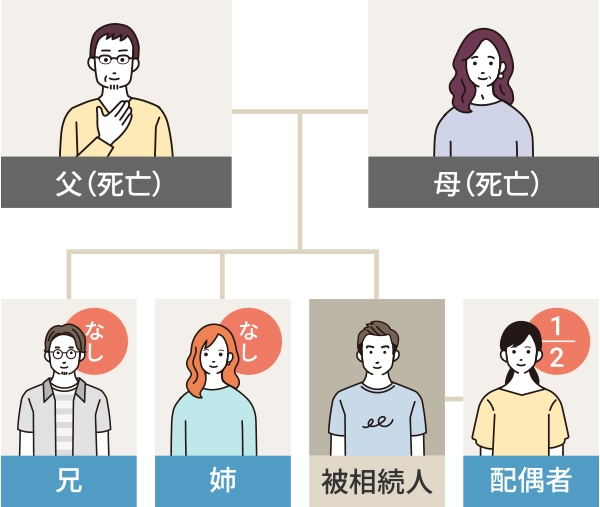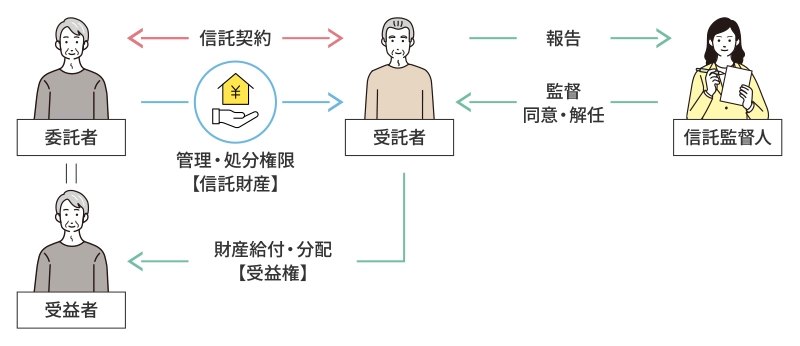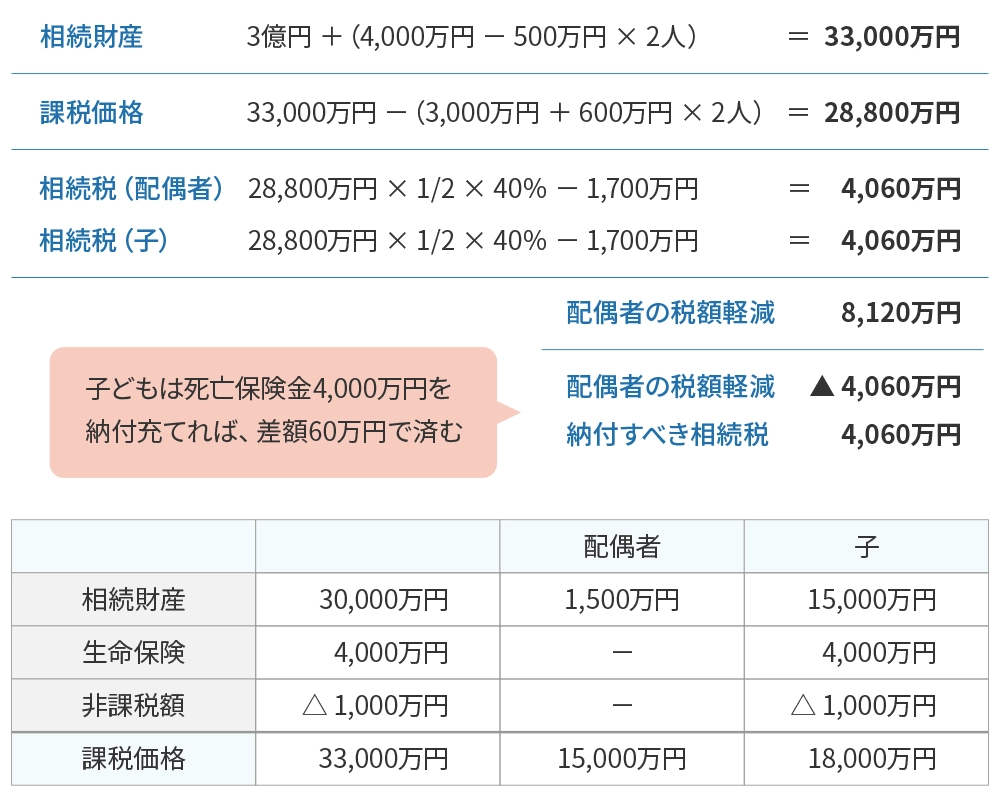財産評価
財産評価とは
相続税の課税財産は、相続、遺贈により無償で取得した財産であるため、その課税価格を計算するために、取得した財産をいくらに見積もるかという「財産の評価」が必要となります。
当社では複雑な財産評価を、適切な判断と計算で算出いたします。
財産の評価に関して、その財産の取得価額による原価主義と、その取得時の時価による時価評価の二つの方法が考えられるますが、相続税法では、時価評価を基本原則としています。
これは、相続税又は贈与税のような財産課税にあっては、相続などにより取得した財産を、その取得時の時価により評価することが、納税者の側からみて最も共通的な判断基準として受け入れることができるし、評価基準としても最も一般性、普遍性を持つ尺度として考えられることによるものでです。
時価とは
相続、遺贈により財産を取得した時点であり、財産を取得した時点とは、原則として相続の開始の時とされます。
財産評価基本通達※では、この取得の日を「課税時期」と定めています。
財産評価基本通達では、「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。」としています。
これは、客観的な交換価値を示す価額、すなわち、買い進みや売り急ぎがなかったものとした場合における価額となります。
「財産評価基本通達」とは相続税・贈与税を計算する際に対象財産の価額評価基準として国税庁が定めているもの。
01土地家屋の評価
相続税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。
1.土地
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
(イ)路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

(ロ)倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。
路線価図及び評価倍率表並びにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。
2.家屋
固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
3.その他
- ①賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
- ②相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
- ③負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。
02上場株式の評価
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
- ①課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
- ②課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
- ③課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
上場株式の価額は、「上場株式の評価明細書」を使用して評価することができます。
上場株式の評価を相談03非上場株式の評価
非上場株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
1.原則的評価方式
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。
(イ)大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して評価する方法です。
なお、類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。
(ロ)小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
(ハ)中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
2.特例的な評価方式
取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
3.特定の評価会社の株式の評価
次のような特定の評価会社の株式は、原則として、①~⑤については純資産価額方式により、⑥については清算分配見込額により評価することになっています。
なお、①~④の会社の株式を取得した同族株主以外の株主等については、特例的な評価方式である配当還元方式により評価します。
- ①類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」のうち直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである会社(比準要素数1の会社)の株式
- ②株式等の保有割合(総資産価額中に占める株式、出資及び新株予約権付社債の価額の合計額の割合)が一定の割合以上の会社(株式等保有特定会社)の株式
- ③土地等の保有割合(総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合)が一定の割合以上の会社(土地保有特定会社)の株式
- ④課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の直前期末の比準要素がいずれもゼロである会社(開業後3年未満の会社等)の株式
- ⑤開業前又は休業中の会社の株式
- ⑥清算中の会社の株式
以上それぞれの評価方法に応じて、この取引相場のない株式の評価をするときには、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を使用していただければ比較的容易に株価の計算ができるようになっています。