税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
税理士法人日本会計相続センター|札幌・北海道の相続税対策を専門とする事務所
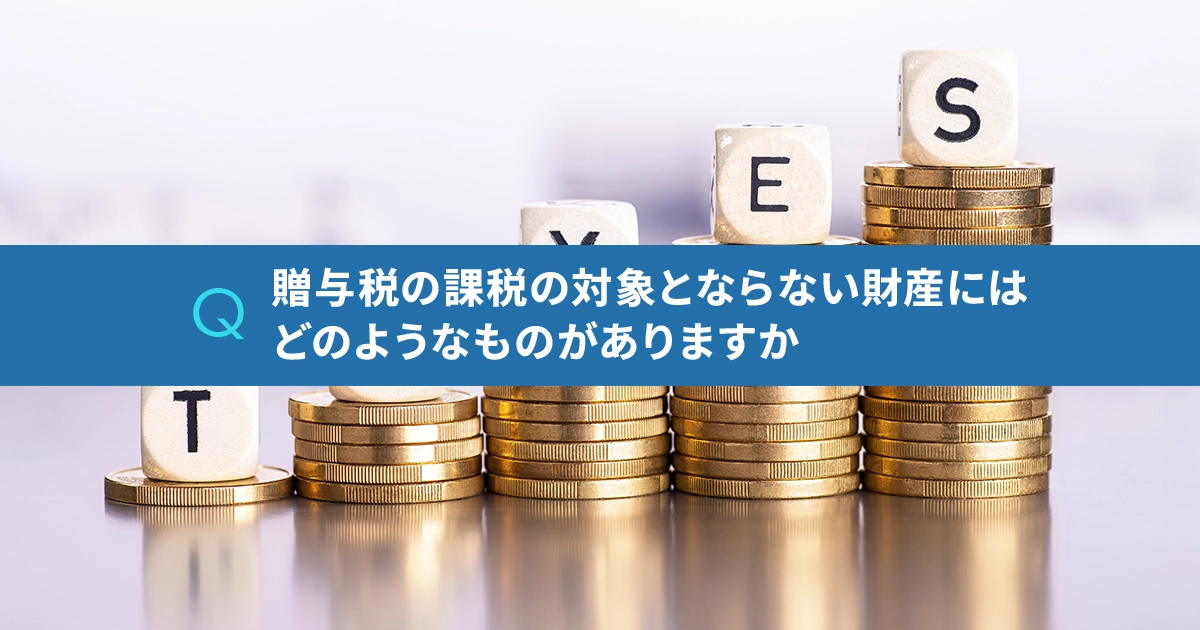
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税(一時所得)がかかります。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用であり、また教育費とは、学費や教材費、文具費などです。これは、日常生活に通常必要な費用に対して、扶養義務に基づいて贈与されたものについてまで課税するのは妥当ではないからです。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
なお、贈与により取得した財産を、取得から2年を経過した日においても事業で使われていない場合は贈与税の対象となります。
奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの。
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。
公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの。
国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。
なお、制限納税義務者および非居住無制限農政義務者についてはこの非課税制度の適用はありません。
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの。
直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの。
直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの。
直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの。
なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。
居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金を夫婦間で贈与した場合、一定の条件を満たすと最高で2,000万円まで非課税になります。
つまり、基礎控除額110万円と合わせて最高2,110万円まで贈与税がかからなくなります。
これは「贈与税の配偶者控除」と呼ばれるもので、利用できるのは主に次の条件を満たす場合です。
翌年3月15日までに実際に居住していることと、その後も継続して住むことが条件になっています。贈与を受けたものの、結局その後に資産を売却した場合には、配偶者控除を適用できないことがあるので注意してください。
また、配偶者控除の適用を受けるためには贈与税の申告が必要です。
贈与を受けたのに申告をしないと、配偶者控除を受けられないだけでなく、延滞税や無申告加算税などの罰則を科されてしまうため注意が必要です。
せっかく受け取った資産が税金や罰金の分だけ減ってしまうことにもなりかねません。
贈与税の配偶者控除の活用を検討する場合には、贈与税に詳しい税理士に相談したり、国税庁ホームページ(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)の記載内容なども確認すると良いでしょう。
父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住む居住用家屋の新築、取得または増改築等に充てるための金銭を贈与された場合、一定の条件を満たすと最高で3,000万円まで非課税になります。
家を買う資金を親が子に援助するようなケースが該当し、利用するには主に次のような条件を満たすことが必要です。
また、非課税になる限度額は、住宅取得の契約日や省エネ住宅かなどによって次のとおり異なります。いずれにしても相当に大きな金額が非課税になることは間違いありません。
| 契約締結日 | 省エネ等住宅控除額 | 左記以外の住宅控除額 |
|---|---|---|
| 〜平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成28年1月1日〜令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
| 令和2年4月1日〜令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
| 令和3年4月1日〜令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
| 契約締結日 | 省エネ等住宅控除額 | 左記以外の住宅控除額 |
|---|---|---|
| 平成31年4月1日〜令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 令和2年4月1日〜令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 令和3年4月1日〜令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
この特例制度を利用するには、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日に税務署で手続きが必要です。非課税制度を利用すると贈与税が0円になる場合でも、手続きをしないとそもそも適用できないので注意してください。
手続き時に必要な書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)は、国税庁ホームページ(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)で確認したり事前に税務署に問い合わせて確認することをおすすめします。
父母や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の方が教育資金に充てるための金銭を贈与された場合、一定の条件を満たすと1,500万円まで非課税になります。
入学費用や授業料として親や祖父母が子や孫にまとまったお金を渡すような場合が該当しますので、そのような場合にぜひ活用したい非課税制度です。
利用するには主に次のような条件を満たす必要があります。
税務署での面倒な手続きが不要で、金融機関の窓口で手続きが済む点が大きなメリットです。
教育資金以外の目的で資金を引き出したり使うことができなくなるため、資産を贈与する側にとっては他の目的でお金が使われる心配もなくなります。
贈与税が非課税になる枠も1,500万円までと非常に大きく、子や孫が中学・高校・大学に入学するタイミングなどで、当非課税制度の活用を検討してみると良いでしょう。
国税庁ホームページ(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税)
父母や祖父母などの直系尊属から、20歳以上50歳未満の方が結婚・子育て資金に充てるための金銭を贈与された場合、一定の条件を満たすと1,000万円まで非課税になります。
子が結婚するタイミングや孫が生まれた時にまとまったお金を渡すような場合が該当しますので、そのような場合にぜひ活用したい非課税制度です。
利用するには主に次のような条件を満たす必要があります。
税務署での面倒な手続きが不要で、金融機関の窓口で手続きが済む点が大きなメリットです。
贈与税が非課税になる枠も1,000万円までと非常に大きくなっています。
結婚や子育てによりお金がかかるタイミングで、当非課税制度の活用を検討してみると良いでしょう。
国税庁ホームページ(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税)
障害者への贈与は、特別障害者の場合には6,000万円までが非課税になり、特別障害者以外の場合には3,000万円までが非課税になります。
この制度を利用するには、信託会社に資金を信託するとともに、信託会社を経由して障害者非課税信託申告書を提出することが必要です。
信託した資産は障害者の生活費などとして使うことができ、信託会社から定期的に交付される仕組みになっています。
贈与税は、一般的に1月1日から12月31日の1年間の贈与に対して税金がかかります。
1年間に受けた贈与額を基準として課税するこの制度を「暦年課税」と呼びますが、贈与税では「相続時精算課税制度」という異なる課税制度を選択することも可能です。
相続時精算課税制度を適用するためには手続きが必要で、何も手続きをしなければ暦年課税が適用される仕組みになっています。
相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円の贈与までは贈与税がかかりません。
ただし、贈与した方が亡くなって相続が開始した際に、贈与した財産の価格が相続税を計算する際に課税対象として加算されます。結果的に相続税が高くなるケースもあるため、どちらの課税制度が良いのかは一概には言えません。
なお、相続時精算課税制度を利用するには、主に次のような条件を満たすことが必要です。
また、相続時精算課税は一度適用すると暦年課税に戻すことができないため注意が必要です。
相続時精算課税を選択すると、暦年課税で使える基礎控除110万円の非課税枠がそれ以降使えなくなります。

© 税理士法人 日本会計グループ All Rights Reserved.